これからインナーガレージ付きの住宅を検討している方へ。
我が家は「ガレージを最優先に据えて」間取りを設計した家です。
設計段階でガレージを先に固定したことで、間取りが一気に決まりました。
この記事では、ガレージの仕様をどう決めたか、そしてその仕様が間取りにどんな影響を与えたかを、実際に5年住んでわかった実感ベースでまとめていきます。
元々車が好きだった私は、家を建てるなら絶対にインナーガレージをつけたいと思っていました。
そのため「ガレージをつけること」を前提条件にして設計士さんに間取りを組んでもらいました。
結果として — ガレージが間取りの起点になり、1階13畳・2階リビングという一般的ではない構成の家が完成したのです。
まずは、そのガレージ部分の仕様から順に共有します。
ガレージの仕様(我が家がこう決めた理由付き)
ガレージは「1台+メンテナンスができる余白」を前提に
幅3.5m × 奥行7m で設計しました。
(=ただ停めるだけではなく、車の横にある程度の作業ができる余裕を確保)
仕様と選択理由は以下の通りです。
シャッター
文化シャッター/巻取り式・電動
└ オーバースライドより安価+高さ確保のため。スマホ操作非対応は少し後悔。
換気扇
パナソニック パイプファン FY-08PDE9D(車の暖気・排気ガス対策として必須)
└ 今思うとそもそも容量不足かも。
照明
片側:ダウンライト
反対側:ダクトレール+スポット
└ 通常使用は満足。作業用照明不足は後述の後悔ポイント
床材
コンクリート仕上げ(後にDIYでエポキシ塗装)
└ コスト重視で当初は打ちっぱなしに
壁
下部:コンクリート
中段:防水キッチンパネル
上段:壁紙
コンセント
片側前後に屋外用コンセント2箇所
└ 当時は十分だと思ったが、使用してから後悔あり(後述)
窓
・縦長の開閉窓 ×3
・室内側に向けた大きめのFIX窓
└ 室内からの鑑賞用として導入
出入口
家につながる勝手口を1箇所
└ 荷物運搬・雨天対応として導入。幅で後悔あり(後述)
インナーガレージで「やってよかった」と思う3つの仕様
1|電動シャッターにしたこと
電動シャッターは間違いなく「つけて良かった設備」です。
リモコン1つで開閉できるため、雨の日・夜間・荷物が多い日でもストレスがありません。
手動シャッターだと
「開け閉めが面倒 → 使わなくなる」
という未来がはっきり見えていたので、ここは投資して正解でした。
デザイン的にはオーバースライドが好みでしたが、
・価格がさらに上がる
・有効高さが低くなる
という理由で、総合判断として巻取り式電動に。
なお最近はスマホ操作対応モデルも出ています。
我が家はリモコン式のみですが、
荷物+スマホ+カギ だけで完結する運用 を考えると
スマホ対応モデルの方が実用的だと思います。
2|家とつながる勝手口
ガレージ直結の勝手口も「便利さで言えばトップクラス」です。
以下の場面で特に役立ちます:
- 雨の日に濡れずに室内へ移動
- 深夜帰宅時に外に出ずに入室
- 買い物したものを室内へダイレクト搬入
- 虫が入るのを避けたい夏場の積み下ろし
「ガレージ → 外 → 玄関 → 室内」と回り道する生活は想像以上に不便です。
勝手口は生活のストレスを一段減らしてくれます。
3|書斎から愛車を眺められるFIX窓
これは完全に“趣味の領域”ですが、
「座ったら愛車が視界に入る」 というのは想像以上に満足度が高いです。
我が家は1階の書斎カウンター越しにちょうど愛車が視界に入るように設計しました。
仕事の合間にふと目線を上げると、そこに自分の車がある──
車好きにしかわからない幸福ですが、これは毎日の楽しみです。
「こうしておけばよかった」と実際に後悔した5つ
家は住んでみて初めて分かる──その典型だったのがこの5項目です。
1|床を「コンクリート打ちっぱなし」にしたこと
コンクリ床そのものは悪くありません。
問題は「打ちっぱなしのまま」にした点でした。
- 雨で濡れた車を入れると湿気が抜けずジメジメする
- 椅子などの木製品にカビが出る
- タイヤワックス・オイル跡が染みになり残る
- 見た目がすぐに“くたびれる”
解決策は2択
- タイル仕上げ(高額/最も美観◎)
- コンクリート塗装(エポキシ等)(費用◎/実用◎)
私は結局、新築3年後にDIYでエポキシ塗装しました。
ガレージの床仕上げについては別記事で詳しく書く予定です。
2|コンセントを「片側2箇所のみにした」こと
当時は「前後にあれば十分でしょ」と思っていましたが──
ガレージ中央には車がいる のを完全に忘れていました。
車を挟んで反対側から延長コードを回すと
・ケーブルが車に接触
・見た目が悪い
・作業性が落ちる
結論:
前後+左右=4方向配置が正解 です。
費用差は微々たるもので、満足度のリターンが大きい部分でしたので、ここは後悔しています。
3|照明と換気扇を「同一配線」にしたこと
我が家はセンサー作動で
「車が入る=照明+換気扇が同時にON」
という仕様にしてしまいました。
当時は合理的だと思ったのですが──
- 「作業するのに照明だけ点けたい」
- 「早朝に暖気のため換気だけ回したい」
→ 不可
スイッチでもどちらも強制連動。
建築後の分離は現実的に困難。
これは完全に“考えが浅かった失敗”です。
4|勝手口の「幅が狭かった」こと
勝手口自体は大正解。
ただし、幅が標準より狭い仕様 になっていました(気づいたのは完成後)。
影響は想像以上で
- 大きな荷物を持って通りにくい
- 後付けスマートロックが干渉して取り付かない
ガレージ勝手口を採用する方へ:
使い勝手は“有無”ではなく“仕様”で決まります。
幅の確認は必須です。
5|ガレージ照明が「暗すぎた」こと
仕様としては
ダウンライト3+スポット3 の計6灯。
日常運用には支障なし…ですが
- 洗車の拭き上げ
- コーティング作業
- FIX窓から愛車を眺めるとき
このどの用途でも 「もう一段明るさが欲しい」 と感じます。
さらに失敗だったのは “暖色” を選んでしまったこと。
車を照らす照明としては相性が悪いです。
理想は
作業灯(白色LED)を天井 or 壁面に追加で確保
コーティングブースのあの感じのイメージが一番近いと思います。
「ガレージ仕様」を最優先にした結果、間取りはこうなった
我が家の間取りは、端的に言うと
「1階=車/2階=暮らし」 という構造に着地しました。
理由はシンプルで
インナーガレージを設置した結果、1階に居住スペースは入らなかった からです。
結果として
- リビングからの眺望が良く、採光も十分
- リビングが道路からほぼ見えない
- 車はガレージで守られる
1階を“車中心”に振り切ったからこそ成立した構造ですが、
その分、満足度は明確に高いです。
まとめ:ガレージは「趣味」ではなく「生活装置」
多くの人が
「ガレージは嗜好品」「余裕のある人の贅沢」
と捉えがちですが、住んでみて思うのはむしろ逆で、
- 外気・雨・暑さ・盗難から守る
- 積み下ろしの負荷を減らす
- 労力と時間を節約する
これは完全に “生活側の利益” です。
そしてそのうえで
「愛車が生活と同じレイヤーで存在する」
という精神的な充足が副産物としてついてくる。
だから私は、
「インナーガレージは趣味ではなく生活装置」
という結論に落ち着いています。
余談:インナーガレージは車を出してしまえば、全天候型の遊び場として活用できます。

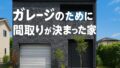

コメント